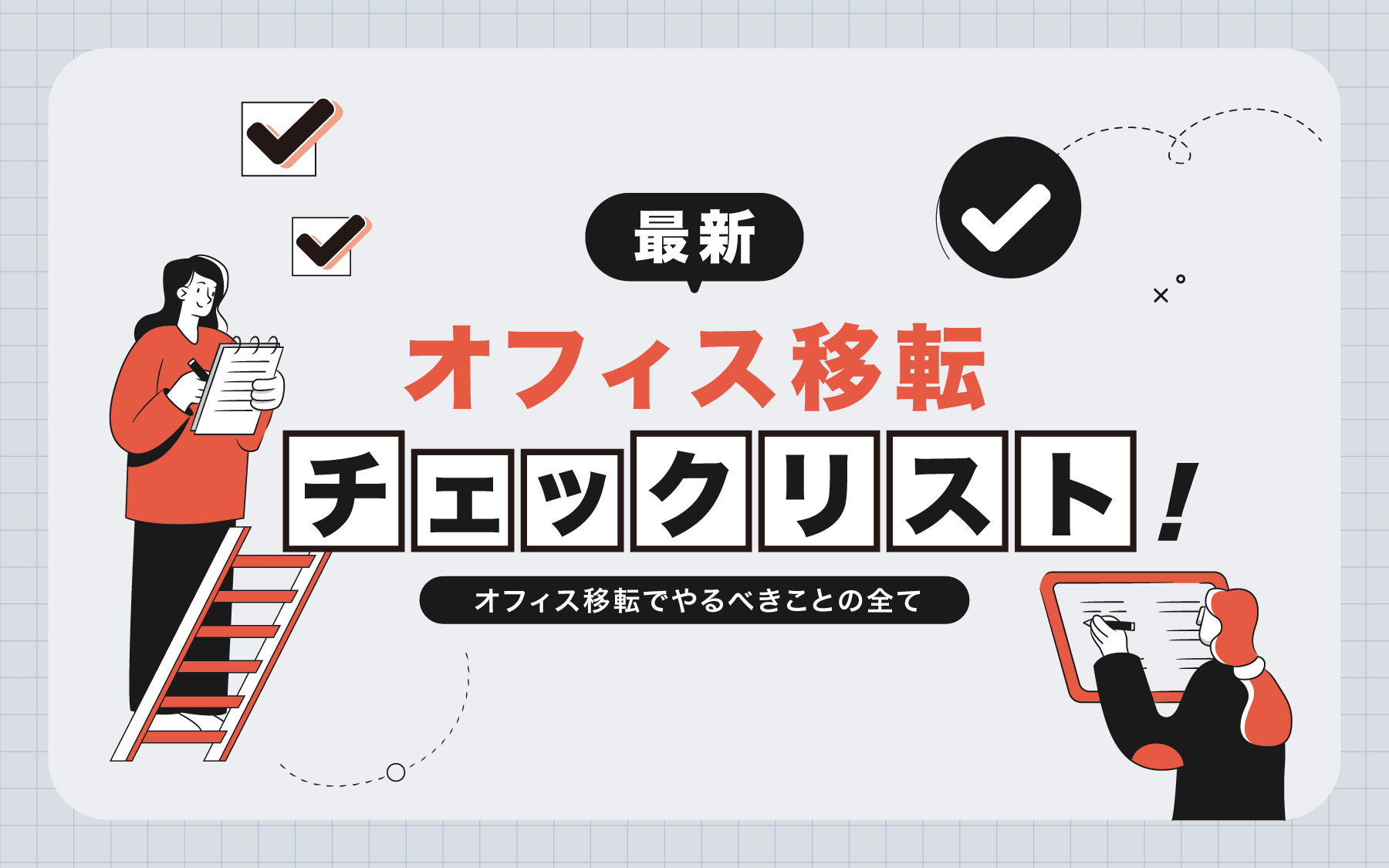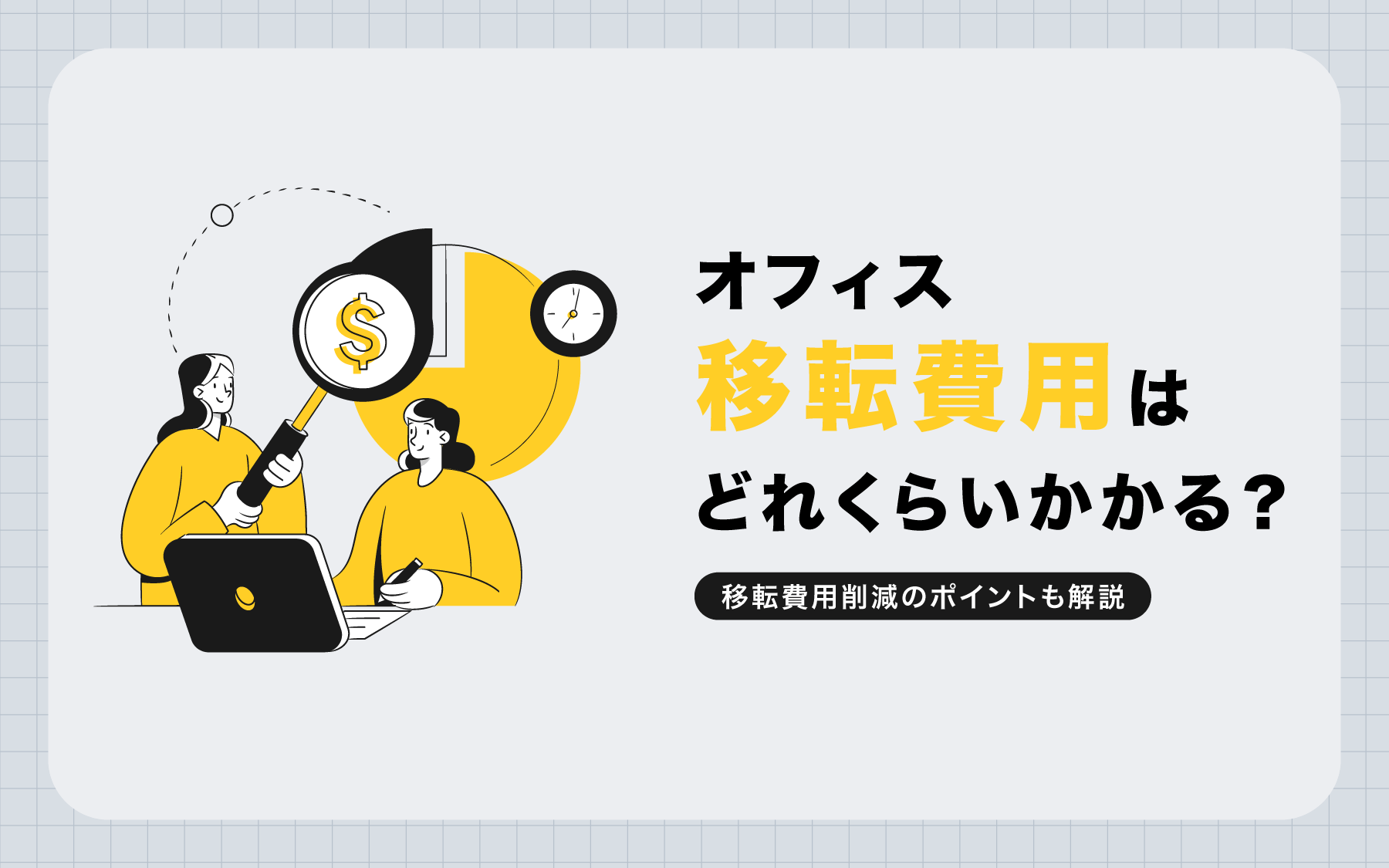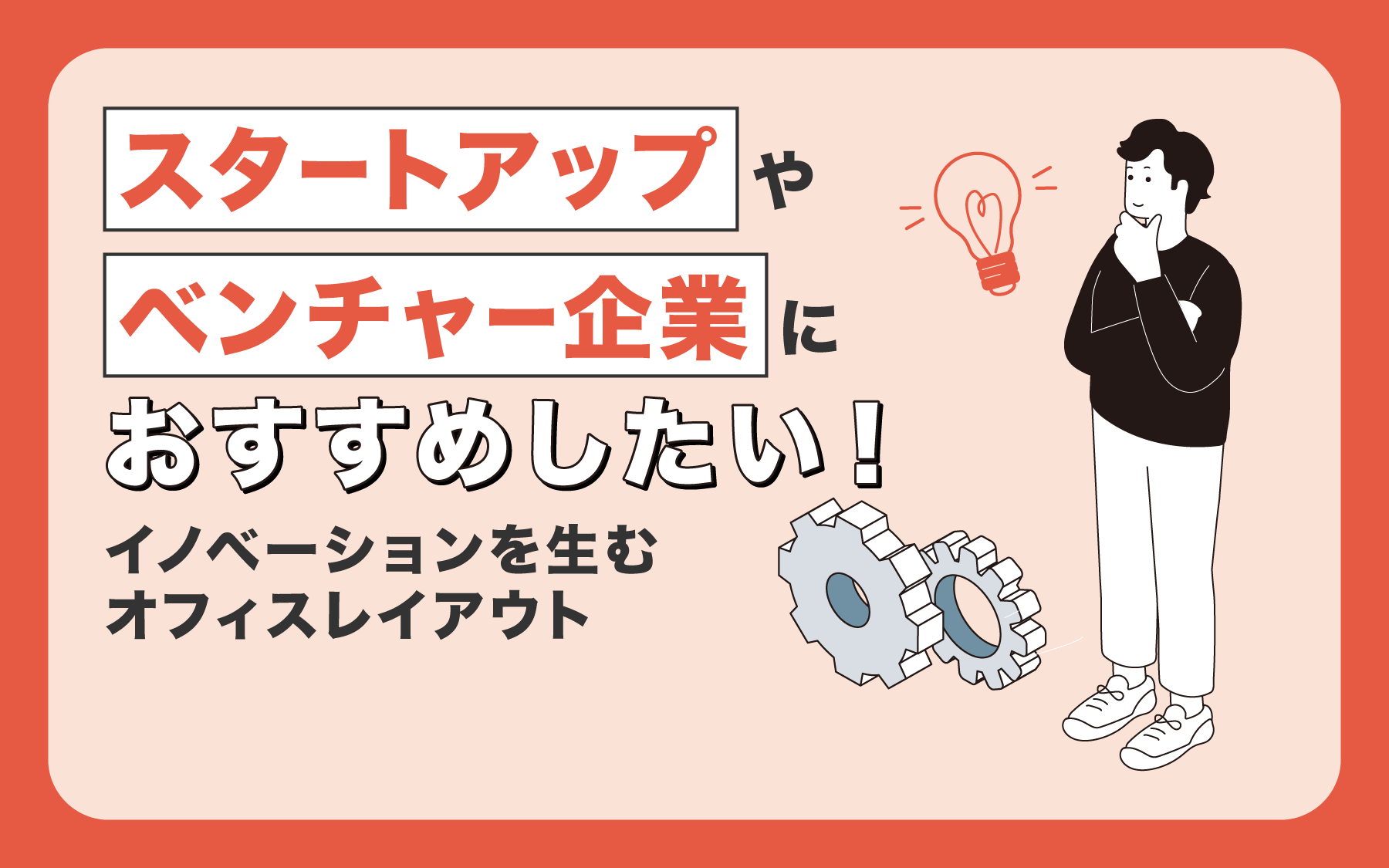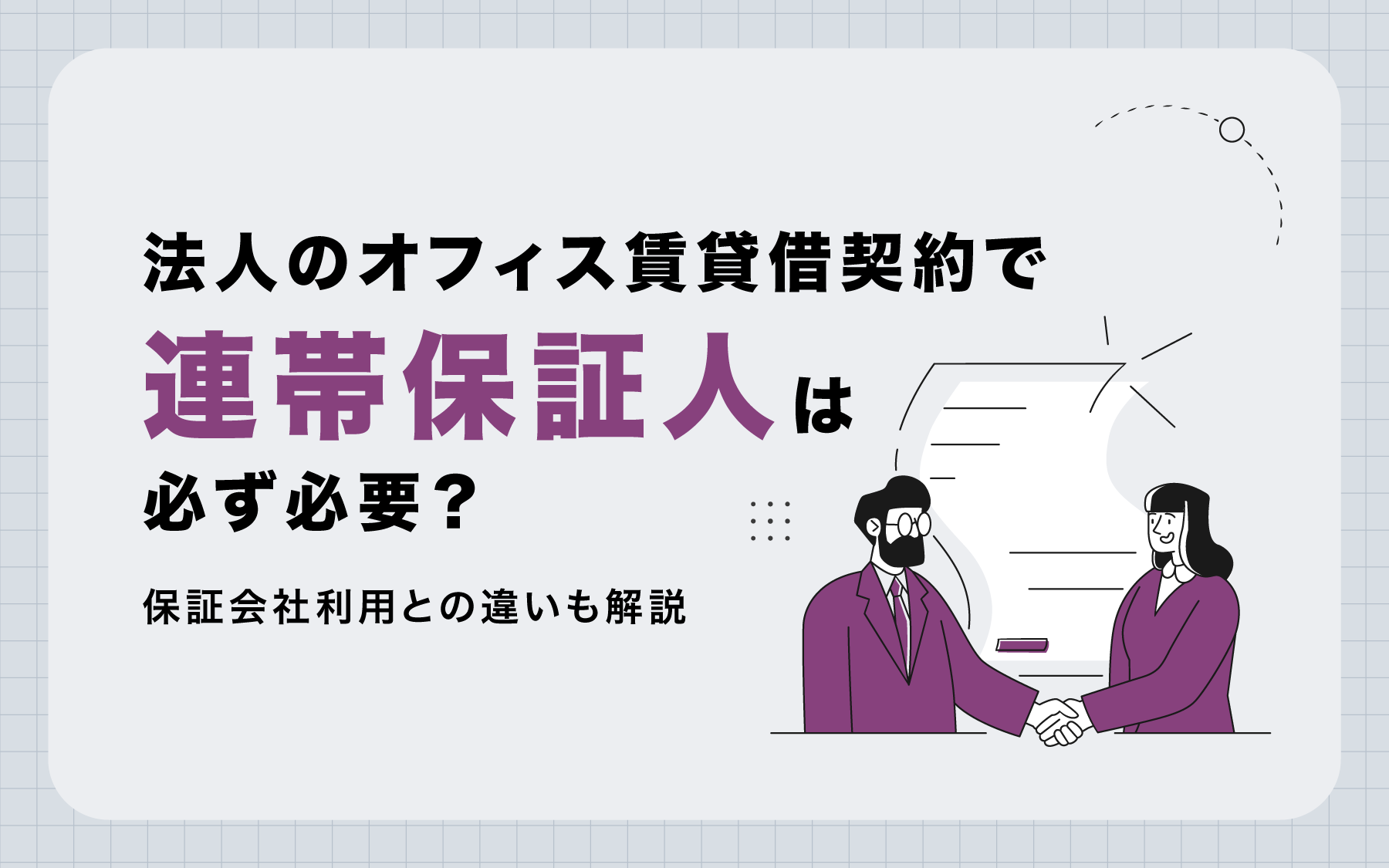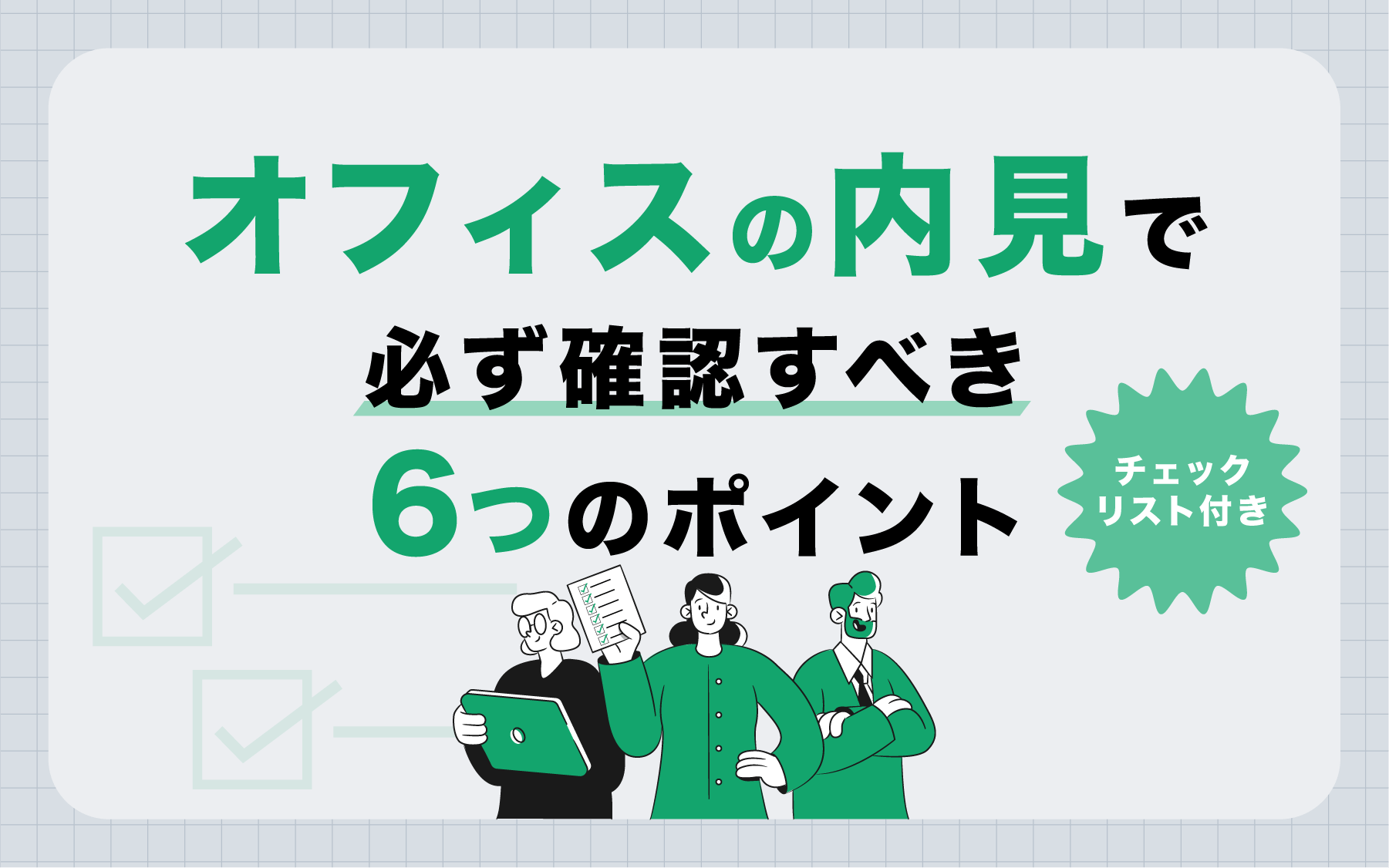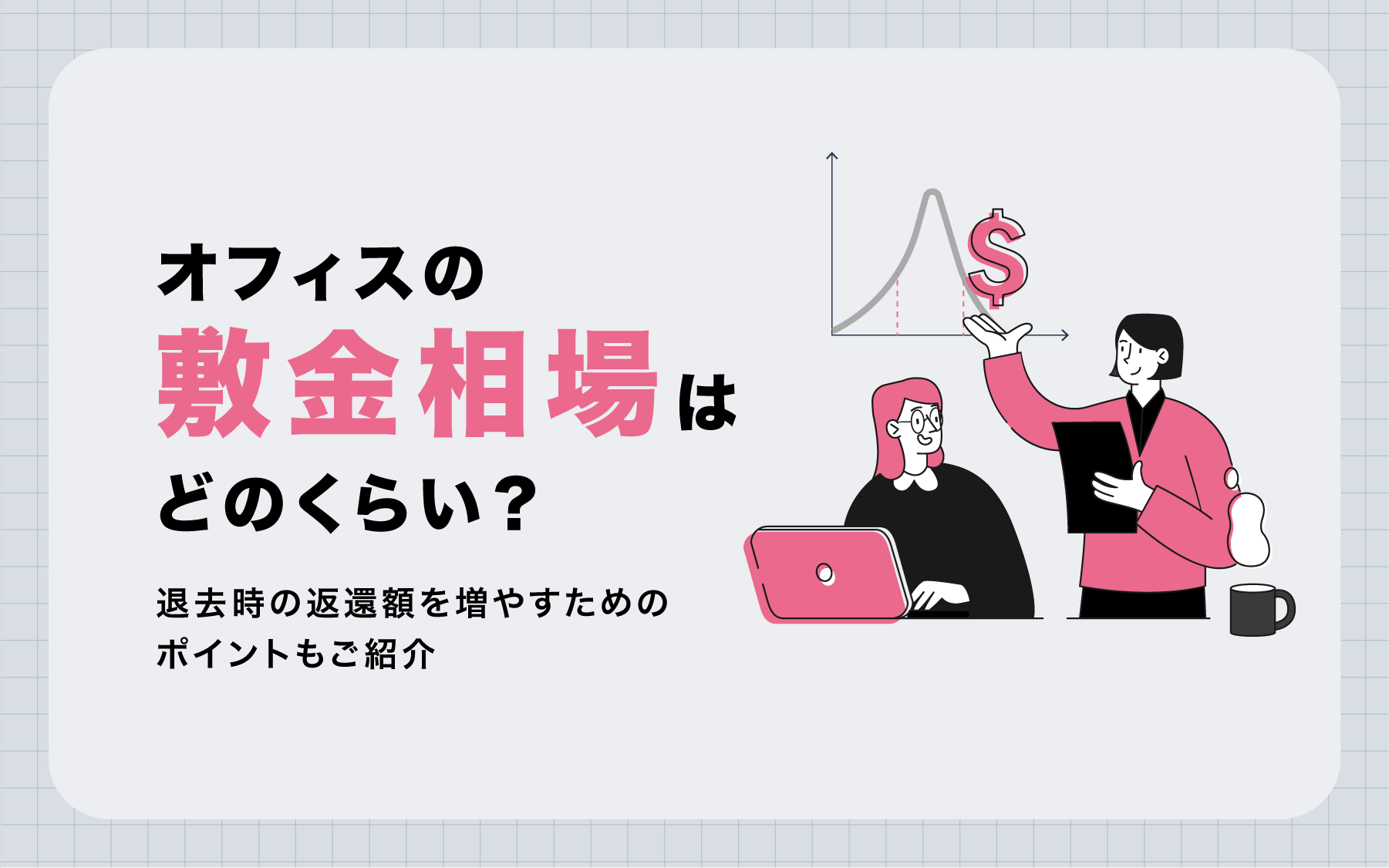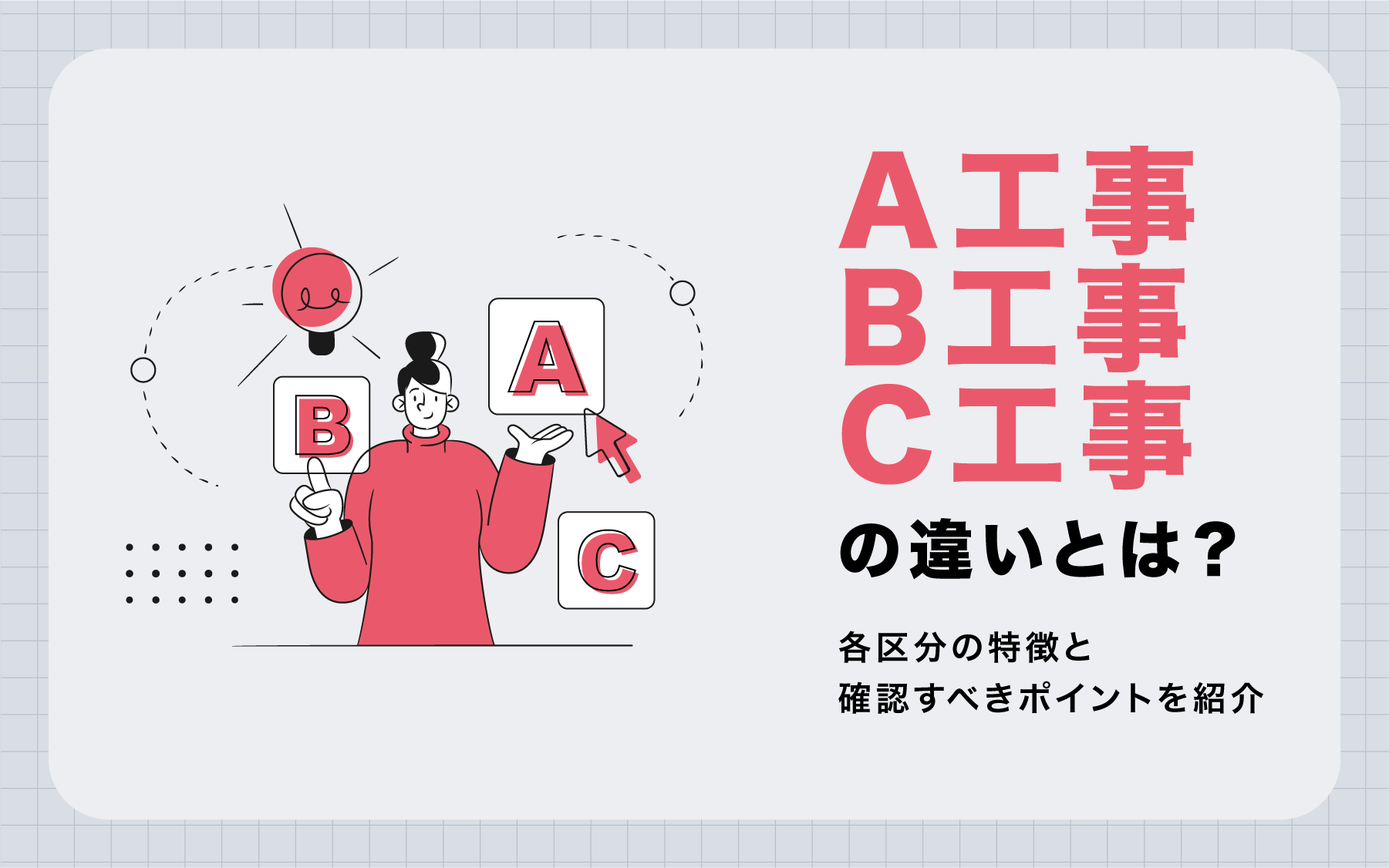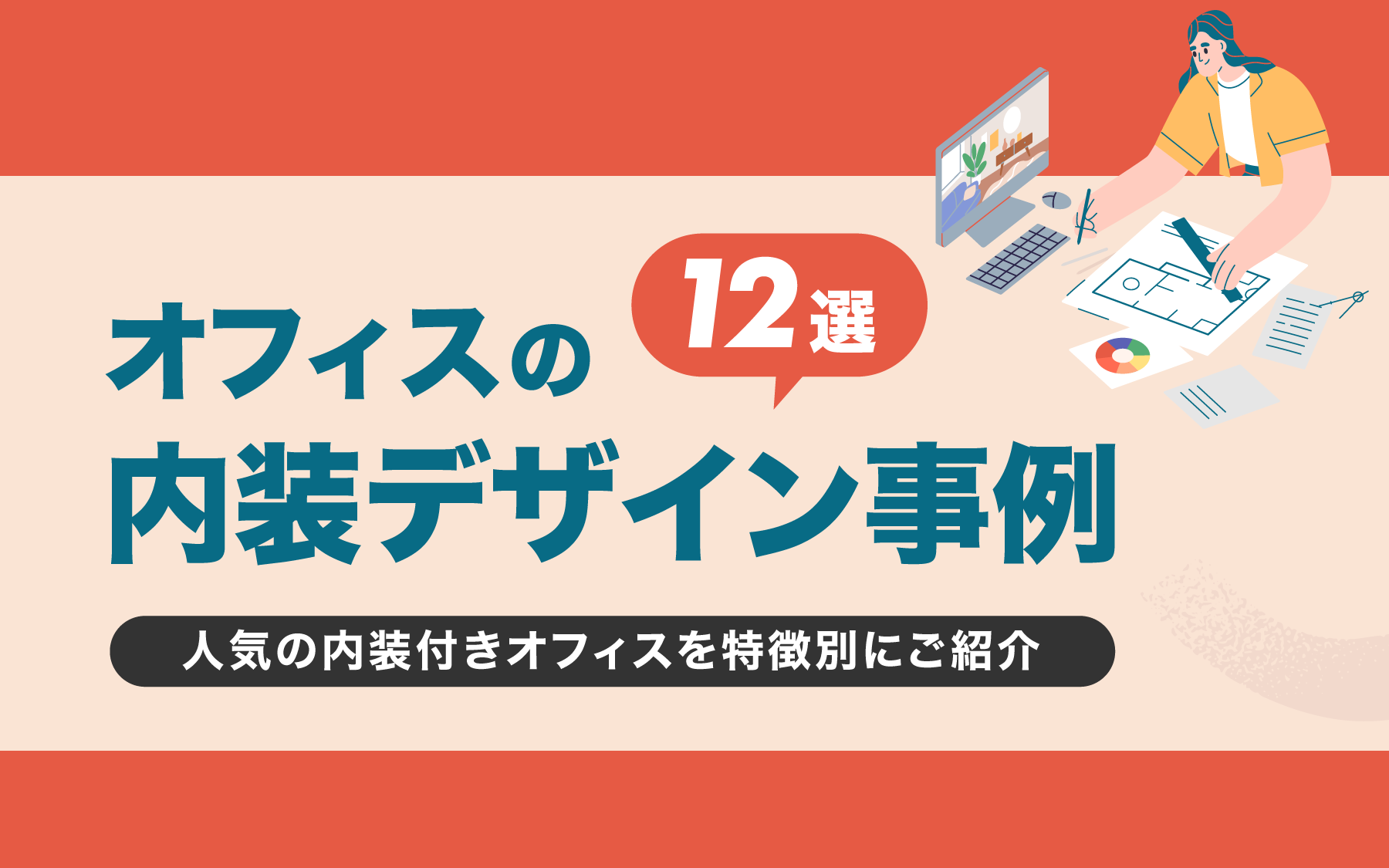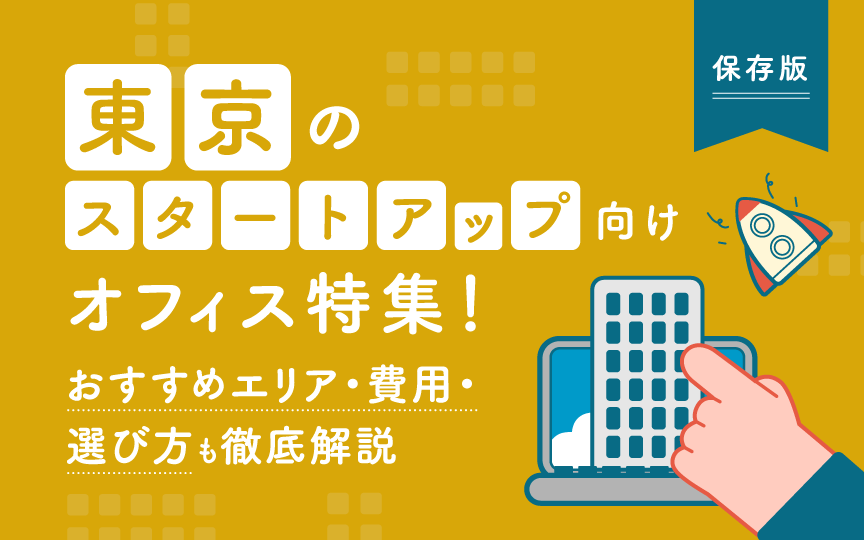オフィス移転のスケジュールごとにやることとは?失敗しない進め方
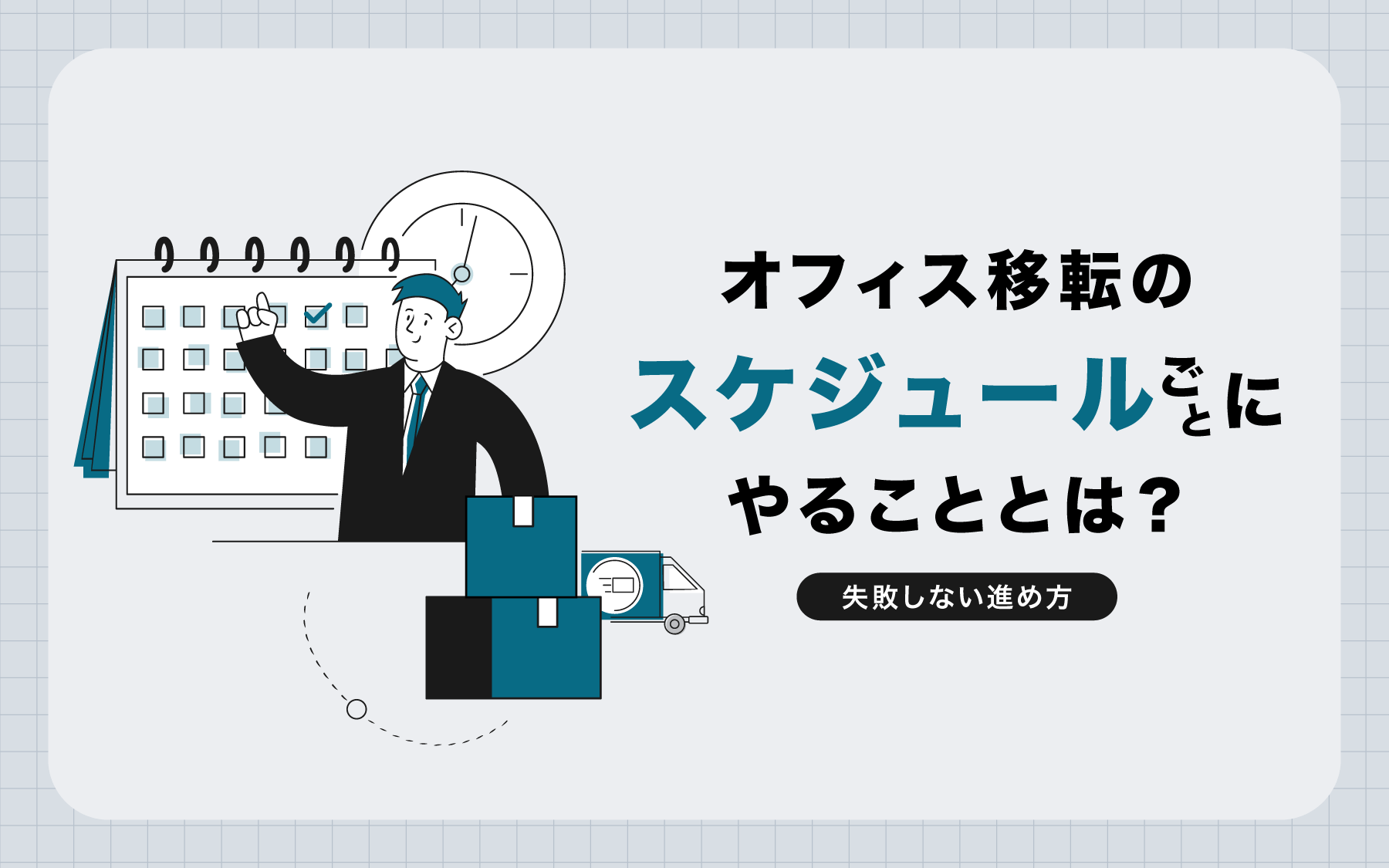
目次
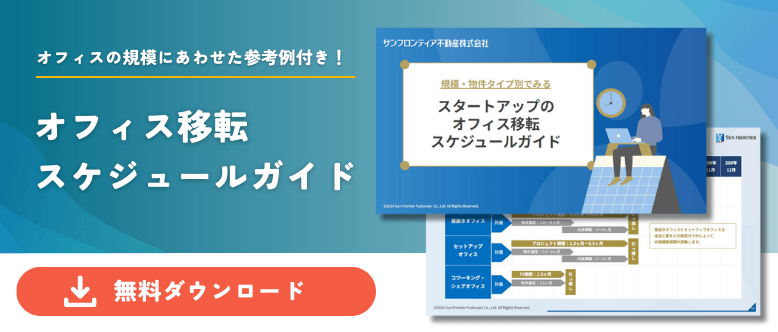
オフィス移転は、スケジュールごとにやるべき業務が数多くあります。この記事では、計画策定から物件選定、内装工事、引越し、運用後までにやるべきことをスケジュールごとに網羅しています。その期間に本来すべきことが漏れてしまうと、プロジェクトの遅延につながってしまい、余計なコストや手間がかかってしまう危険があります。オフィス移転をお考えの経営者や担当者の方は、是非ご一読ください。
目次
オフィス移転でやるべきこととは? スケジュール通りに行わないと遅延のもとに
オフィス移転では、やるべきことが数多くあります。円滑に移転を進めるためにも、やるべきことを一つずつ確認していきましょう。
オフィス移転でやるべきこと
- 計画・予算策定
- 物件選定と契約
- デザイン・設計
- 工事の実施
- 移転後の運用
移転計画の策定から移転までには、およそ半年程度の期間を要することが一般的です。移転したい時期から逆算して、計画の策定に着手するとよいでしょう。
オフィス移転でやるべきことの1~5について、詳しくは次項より説明します。
計画・予算策定(移転約半年前までのスケジュール)
まずは、計画・予算の策定です。前述したとおり、移転の約半年前までに着手することをおすすめします。ただし、50坪を超える広いオフィスの場合、移転にかかる期間が半年以上にわたる可能性があるため、さらにスケジュールにゆとりをもって取り組みをスタートさせましょう。
この段階では、プロジェクトチームの発足をはじめ以下のような取り組みが必要です。
プロジェクトチーム発足
オフィス移転までには多くの作業が発生します。専門チームを発足させることで、チームメンバーが中心となり移転準備や移転にかかる作業の指示などを行えるようになります。プロジェクトチームを中心に移転を進めることで、作業の効率化が期待できます。
プロジェクトの進捗も把握しやすくなり、円滑なオフィス移転を実現できるでしょう。
現オフィスの課題整理と移転目的の明確化
具体的な計画を策定する前に、現オフィスにある課題の整理と移転目的の明確化を行います。「社員の増加で手狭になったためより広いオフィスに移転したい」「交通の便が悪いので立地の良いオフィスに移転したい」「社員間のコミュニケーションが希薄」など、現在の課題から移転の目的を整理します。
課題を洗い出した後は、将来のビジョンについても整理して、ビジョンと現在のギャップを解消できるような目的・目標を設定します。
要件整理・予算計画
次に、物件に必要な要件を整理して、予算を含めた計画を策定します。物件の要件を整理する際には、最寄駅からの距離や周辺の環境、交通事情、飲食店の有無など、目的に沿って必要な要素を洗い出すことが大切です。
移転計画では、スケジュールや予算、必要な手続きに関してまとめることで、リスクを抑えながら円滑な移転を実現できます。
物件選定~契約(移転5ヶ月前までのスケジュール)
物件の要件整理などを行った後は、物件の選定から契約のフェーズに入ります。この段階で行うことについて詳しく見ていきましょう。
現オフィスに関する確認・解約通知
移転先を決定する前に、現オフィスの契約条件や解約通知期限などを確認します。原状回復工事の範囲や期間、指定業者の有無についてもチェックしておきましょう。
これらを踏まえたうえで、現オフィスの解約通知を行います。ただし、一般的な解約通知予告期日は退去予定日の3〜6ヶ月前ですが、移転先が決まる前に解約通知を出してしまうと、物件が未定のまま3ヶ月後に引っ越しをしなければならないなど、当初のスケジュールから予定がズレてしまうことがあります。
解約通知のタイミングは、移転先が決定してから行うとよいでしょう。
移転先のオフィスの決定
移転先のオフィスは、複数の物件に関する情報を収集し、内見などを行った上で決定します。
物件の情報収集
物件を選定するために、複数物件の情報を集め比較・検討する段階です。内見を実施し、物件の状態や周辺環境を確認します。また、事前に整理した要件を満たしているか改めてチェックしましょう。
契約条件の確認
物件の契約条件の確認も重要です。賃料や契約開始日、契約期間、解約予告期間、違約金、内装工事区分、特約条項、フリーレントの有無などについて細かく把握しておきます。
申し込み・審査・契約まで
申し込みの際には、申込書とあわせて3期分の決算書や今期の試算表、事業計画書などが必要です。
契約時には会社実印・連帯保証人実印とあわせて3ヶ月以内に取得した法人登記簿謄本、法人印鑑証明書、連帯保証人住民票、連帯保証人印鑑証明書などを提出します。
物件の申し込みから審査、契約内容の調整、契約完了までは少なくとも1ヶ月程度かかることが多いです。審査完了後にすぐに入居できるわけではないことを念頭に置いておきましょう。
デザイン・設計(移転4ヶ月~移転2ヶ月前までのスケジュール)
物件が決定した後は、デザイン・設計の段階に入ります。ここでは、以下のような対応が発生します。
内装要件の整理
内装にかかるコストと移転スケジュールの整理、現オフィスの完全退去日を確認します。入居人数や会議室数、収納量、福利厚生スペース、OA機器の必要数量など、設計要件についても整理しておきましょう。
外注する業者へ声掛けしておく
オフィス移転に関するPM会社や内装デザイン・工事会社、回線業者、引っ越し会社など、必要各社への声かけを行います。PM会社に依頼する場合には、必要各社の選定から任せられます。移転にかかる業務負担を軽減したい場合には、PM会社に依頼することを検討してもよいでしょう。
オフィスプランニング
オフィスレイアウトや配置する什器などを含めて検討し、コンセプトや目的が体現されたプランになっているかを確認する段階です。
コンセプト策定
移転の目標や目的に沿ったコンセプトを策定します。例えば、フルリモートから出社制に戻すことが目的の場合には、「出社したくなるオフィス」をコンセプトにするといったイメージです。
レイアウト設計
オフィス内の各エリアに何を配置するかを決定します。工事見積作成依頼前にレイアウトを確定させることが望ましいものの、レイアウト設計をスムーズに決めるのは難しいでしょう。
そこで、費用に大きく影響する「間仕切りの位置」を、工事見積依頼前に優先して確定しておくと安心です。これは、間仕切りを立てる位置に天井設備があると移設や撤去が発生してしまうためです。
天井設備にかかる費用は高額なことを加味して、先に間仕切りの位置を決めておきましょう。
工事見積作成
工事見積作成の段階では、優先度をつけてコスト削減の検討ができているか、移転の目的がコスト削減により失われていないかを確認します。
オーナーが工事会社を指定し、工事費用を借主側が負担するB工事のケースでは、工事見積の依頼から見積提出までには1ヶ月~1ヶ月半程度の期間を要します。それから減額検討を行い発注へと進むため、スケジュールに減額検討期間を含めておくとよいでしょう。
減額検討期間がない場合、見積提出から減額検討をせずに発注せざるを得なくなり、不要なコストが発生しがちです。
既存家具の取扱い
既存の家具を移転先でも利用するか、廃棄するかを検討します。新オフィスに転用できる家具の有無を確認しましょう。
新たな家具が必要な場合には発注のタイミングにも気を付ける必要があります。家具は工事完了後から引っ越し直前に納品されることが多いため、工事の発注よりも少し後に期限を設定されます。既製品であれば発注から納品にかかる期間は2週間から1ヶ月、特注品は1ヶ月半から2ヶ月程度の期間を要するため、余裕を持って発注しておきましょう。
その他(セキュリティラインの設定、インフラ・導線)
セキュリティラインの設定では、社内・社外のセキュリティをどこで設けるかなどを決定します。インフラ・導線においては、回線が扱いやすくなっているか、邪魔にならない配置となっているか、オフィスを利用する人数に対して十分なスペックとなっているかを確認しましょう。
工事の実施(移転1ヶ月~移転当日までのスケジュール)
オフィスプランニングや見積が確定した後は、いよいよ工事がスタートします。ここからは、工事の実施から移転当日までの流れをご紹介します。
業者各社へ工事・引越しなどを発注

内装工事、家具、回線、引っ越し・廃棄、セキュリティ、AV機器や社内備品など、新オフィスに必要なものに関わるさまざまな会社に発注します。
発注時に注意すべき点に、リードタイムがあります。リードタイムとは、発注後に資材や作業員を手配する期間が必ず発生します。そのため、内装工事を発注しても、すぐに着工できるわけではありません。50坪程度のオフィスで、リードタイムは少なくとも2週間、長い場合1ヶ月程度の期間を要することがあります。発注日は、引っ越しの日程と工事期間から逆算して目途を立てておきましょう。
Wi-Fiなどのネットワークでは、リードタイムに3ヶ月ほど必要な場合が多いです。年末年始や3月、9月などの繁忙期では4ヶ月以上かかることもあるため、移転が決まり次第すぐに声をかけて予定を押さえておくことをおすすめします。
また、発注の際には各社と工程確認を行い、鍵の引き渡し日までに工事などが完了するように進めるといいでしょう。
内装工事の実施
内装工事がスタートしたあとは、現場監督や設計会社から工事の進捗報告を受けるようにしておきます。実際に現場を確認したい場合には、「いつ現場に入りたいか」を事前に伝えておきましょう。
また、内装工事の着工に関して、原則”契約開始日以降”となるため、内装に関する検討が進んでいないのに、契約開始日を早い日付で設定してしまうと、使用していないのに家賃が発生する場合もあるため注意が必要です。
各種手続き・届け出
移転には、諸官庁、取引会社などへのさまざまな手続きや届け出が必要です。
例えば、法務局へ「本店移転登記申請書」を提出したり、税務に「納税地の異動届出書」を提出したりと、多くの届け出・手続きが発生します。手続きや届け出に手間取らないよう、事前に必要なものをチェックしておきましょう。
社内ルールの整理・手続き
引っ越しの完了前に、座席表や社内運用ルールを整理しておきます。ごみの分別やセキュリティの操作方法、設備・備品の使い方のルールなども策定しておくと安心です。
社内向けに移転案内を配布したり、新住所が入った名刺を作ったりといった作業も発生します。
施主検査の実施
新オフィスにかかる工事が完了すると、施主検査が実施されます。施主検査とは引渡し前に行われる検査のことで、工事が打合せ通りに行われているか、設備がきちんと動作するか、作業によってできた汚れや傷がないかを工事を行った会社立会いのもとで確認する作業です。工事内容に不備がないかをしっかりと確認しましょう。
引越し準備~実施
移転の1ヶ月前を目安に、引っ越し説明会を実施します。梱包方法や廃棄物の取り扱い、スケジュールについて共有しておきましょう。
引っ越しの1週間前からは、当日問題なく引っ越し作業が完了できるように梱包状況やPCデータのバックアップ状況を確認します。
移転後の運用(移転当日~2ヶ月後までのスケジュール)
引っ越し作業の完了後は、旧オフィスの原状回復工事や関係各社への支払いなどが発生します。
旧オフィス関連
旧オフィスにおいては、原状回復工事の実施と敷金・保証金などの精算が行われます。
原状回復工事の実施
原状回復工事においては、内装工事業者へ発注を行うとともに、工事の工程と完了日を確認しておきましょう。原状回復工事完了後は、旧オフィスの管理会社立会いのもと引渡しの確認を実施します。
敷金・保証金などの精算
旧物件を返還するタイミングを確認し、敷金・保証金などを精算します。このとき、契約をあらためて確認しておき、精算金額が妥当かきちんとチェックすることも大切です。
新オフィス関連
新オフィスにおいては、必要書類の収集と保管、移転に関係した業者への支払いが必要です。
必要書類の収集・保管
新オフィスでの必要書類には、賃貸借契約書、内装の竣工図面、新しい家具や設備の取り扱い説明書、保証書などがあります。これらを収集し、保管・管理を行いましょう。
移転関係の業者へ支払い
PM会社、内装デザイン・工事会社、回線会社、引っ越し会社など、新オフィスへの移転に関係した業者への支払いを行います。支払業務を円滑に進めるためにも、支払期日や金額をあらためて確認しておくと安心です。
プロジェクトの振り返り
すべての作業が完了した後に、プロジェクトを振り返ってみましょう。事前に策定していた目的が達成できているか、また、プロジェクトにおいて良かったことや次に活かせることなどの情報も整理しておきます。再びオフィスを移転する際の参考になるよう、プロジェクト全体についてまとめておくことをおすすめします。
まとめ|オフィス移転でお困りなら、お気軽にサンフロンティア不動産にご相談ください
新オフィスへの移転には多くの手間と時間がかかります。事業開発や市場開拓、さらなる事業規模の拡大など、限られた人手で多くの業務をこなしている企業の場合、オフィス移転にかけられるリソースも限られているでしょう。
サンフロンティア不動産では、オフィス物件探しから移転手続きに関するお悩み・ご相談にも対応しております。オフィス移転でのお困りごとが発生した際には、お気軽にご相談ください。
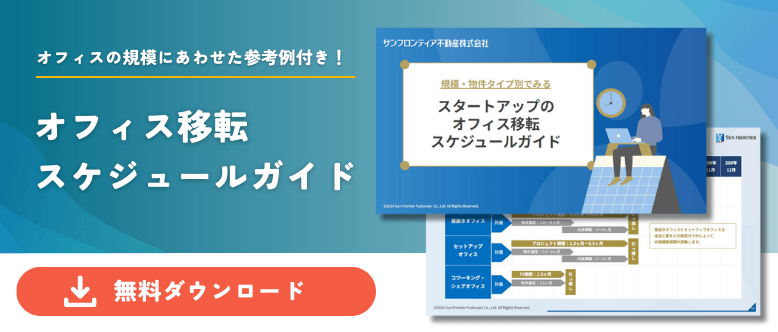

記事監修者
菅野 勇人
宅地建物取引士
セットアップオフィスから一般的なオフィスまで、多種多様なオフィスビルの魅力や特徴を熟知したオフィス物件マニア。
スタートアップ企業の移転支援経験が多く、そこで得た知見を活かし、お客様の理想のオフィス探しを全力でサポートいたします。