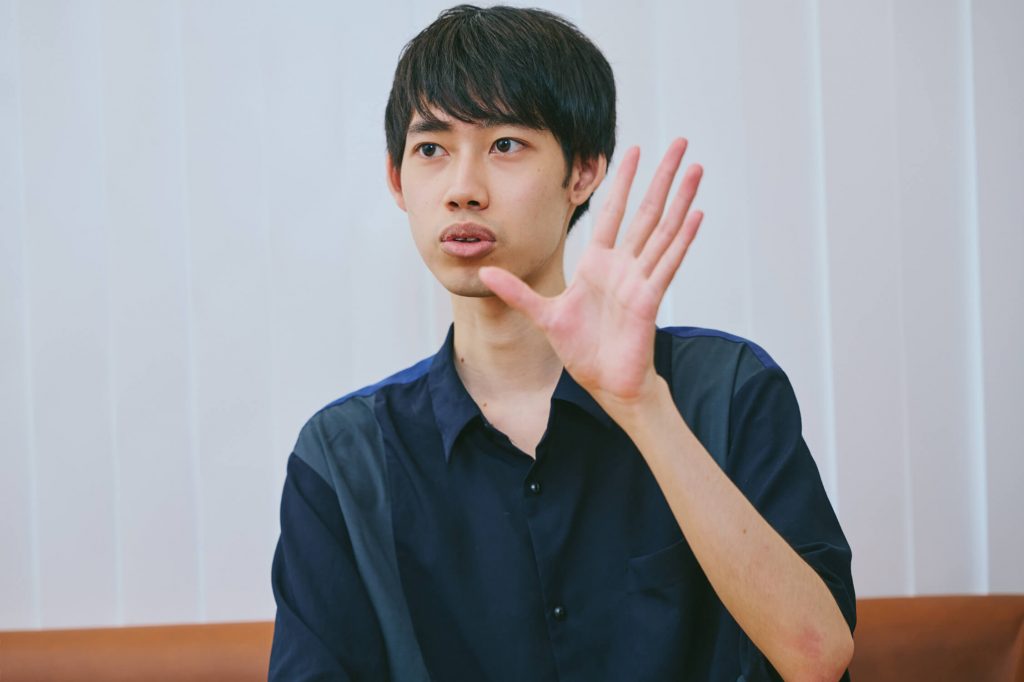東大発スタートアップが選んだ「遊び心あるオフィス」。移転の決め手は成長とカルチャー醸成

コンシューマー向けのアプリケーション開発を手掛けるスタートアップ企業ならではの視点から、シェアオフィスからの移転を決めた背景やオフィス選びのポイント、そしてスタートアップ企業におけるオフィスの役割について、同社代表取締役CEOの髙橋 侑志さんにお話を伺いました。
- 社名:Meltly株式会社
- ウェブサイト:https://meltly.co.jp/
- サービスサイト:https://days-ai.com
- 設立:2022年2月
- 事業内容:AIアプリ「Days AI」の開発・運営
- 住所:〒113-0033 東京都文京区本郷2-26-9 NOVEL WORK Hongo 3階
- お話を伺った方:代表取締役 髙橋侑志さん
- メンバー増加に伴い、オフィスの物理的スペースが不足した
- 組織としての一体感や価値観を共有し、カルチャーを醸成したい
- 採用強化のため、スタートアップ特有の不透明感を払拭したい
- 対面で相談・決定でき、業務のスピードと質がともに向上した
- コンシューマー向け事業らしい遊び心の演出で一体感が生まれた
- 採用決定率が3分の2から4分の3に向上し、採用強化を実現
目次
目次
人と技術が“溶け合う”世の中を目指して。東大発のスタートアップが描く未来とは
―― 社名の由来と事業概要についてぜひ教えてください。
髙橋さん:「Meltly(メルトリー)」は「溶ける=Melt」が由来の造語で、人と技術が自然に溶け合うような社会、つまりAIやテクノロジーが人の日常に溶け込み、美しい体験を生む世界を目指したいという想いを込めています。ロゴはMの文字が溶けるようなイメージで、知人のデザイナーに制作してもらっていました。
弊社では「Days AI」というコンシューマー向けアプリを開発、提供しています。「うちの子」と呼ばれるオリジナルキャラクターをユーザーが自分自身でデザインし、そのキャラの一貫したイラストを作成したり、チャットしたり、他ユーザーと共有できたりと、単なるイラスト生成に収まらないサービスであることが特徴です。
―― オフィス選びにつながる、貴社の働き方や大切にしている考えをお聞かせください。
髙橋さん:コンシューマーを対象としたアプリケーションを提供するという弊社のビジネスモデルでは、社員数と売上規模は必ずしも比例するわけではありません。質の高いサービスを提供できるのであれば、たとえ少人数で開発したアプリであっても多くのユーザーに利用してもらえます。
そのため、弊社では質の高いアウトプットを継続的に生み出していくために「どのように働くか」を重視しています。たとえばフレックスタイム制を導入して、24時間いつでもオフィスが使え、いつでも好きな時間に働けるようにしています。オフィスにはゲーミングPCが置いてあり、気分転換やサービス改善に結びつく新しいアイデアのためにいつでもゲームできることも特徴です。遊びと仕事が溶け合うように、それぞれの境界を曖昧にすることが、弊社の働き方で大切にしている考えです。

事業拡大にあわせたスペースの確保とカルチャー醸成に課題。シェアオフィスからの移転を決断
―― 現在のオフィスに入居される以前は、どのようなオフィス環境だったのでしょうか。
髙橋さん:2022年に起業して1年ほどは、自宅を登記して在宅で事業を進めていました。その1年後にEast Venturesさんにご紹介いただく形で、サンフロンティア不動産株式会社さんと共同運営されているスタートアップ向けシェアオフィスの『Hive Shibuya ※』に入居しました。渋谷駅からのアクセスがとても良く、同世代の起業家との横のつながりを作れることが魅力でしたが、入居からおよそ1年半が経ったタイミングで今回セットアップオフィスへの移転を決断しています。
―― シェアオフィスで働かれていた頃は、どのような課題があったのでしょうか。
髙橋さん:サービス拡大とともに、開発や運営に関わる人員が増え始めたことで5名分の座席では足りなくなったことが大きな要因です。ユーザーが増えれば、それに伴って処理すべきトランザクションも増えますし、開発スピードも求められます。特に私たちは画像生成系のAIを自社開発しているので、バックエンドの保守・運用に加え、品質管理やテスト体制の強化も欠かせません。加えて、マーケティングにも本格的に取り組むようになり、専任のメンバーが必要になったという事情もあります。
もう一つの課題が、企業としてのカルチャーをいかに醸成していくかというポイントです。スモールチームであればあるほど、密度の高いコミュニケーションや価値観の共有が重要だと私は考えています。経営合宿のように高密度なコミュニケーションを、日常業務で常にできる環境が整えば、チームとしての方向性はブレにくくなるはずです。オンライン上のやりとりだと表現が難しいニュアンスも、対面であれば自然に共有できるのではないかと期待しました。
そこで出社とリモートのハイブリッドから8割出社の体制にシフトしていくことを決定し、同時期に新しいAIモデルやキラー機能をリリースしたことでユーザー規模が大きく拡大したタイミングで、シェアオフィスからの移転を検討し始めたのです。
『Hive Shibuya』は、Zホールディングス株式会社のコーポレートベンチャーキャピタルである Z Venture Capitalと、日本及び東南アジアで最大級のシード期ベンチャーキャピタルである East Ventures、そしてサンフロンティア不動産株式会社が共同運営するスタートアップ向けシェアオフィス。今後、日本を代表するスタートアップを生み出し、スタートアップの聖地となることを目指している。

自社物件で仲介手数料不要、フリーレント期間の設定。スタートアップ企業に優しい提案
―― セットアップオフィスへの移転は、どのような理由から決めたのでしょうか。
髙橋さん:採用強化の目的でも、私が在学している東京大学と最寄り駅からのアクセスの良さは重要なポイントです。そこで大学からほど近い、神保町や御茶ノ水エリアにある住居兼オフィスのようなSOHO物件を当初は探していました。
しかし、将来的に事業の成長に伴って拡張や移転が必要になることを見越すと、什器を用意する必要がなく、退去時の現状回復費用を抑えられるセットアップオフィスのほうが柔軟性が高く、弊社の規模感と成長戦略に合致していると判断しました。入居準備の手間や費用を最小限にできれば、その分だけ社内のリソースを採用活動やマーケティングなど事業のトップラインを引き上げる施策に集中できます。
―― オフィス移転のパートナーとして、サンフロンティア不動産を選んだ理由をお聞かせください。
髙橋さん:『Hive Shibuya』に入居していた頃、サンフロンティア不動産さんとは席が近く、あいさつなどで自然とコミュニケーションを取っていました。そして今回、セットアップオフィスへの移転をご相談したところ、他の不動産会社さんと比べてもレスポンスが非常に早いことに驚いています。
実際に相見積もりを実施したところ、サンフロンティアさんが所有しているセットアップオフィスでは仲介手数料がかからず、費用面でも優位性がありました。また、フリーレント期間の設定といったオフィス契約についても柔軟に対応いただけるとの提案があったことも高評価です。
―― どのような条件で比較検討を行い、現在のオフィスに決定されたのでしょうか。
髙橋さん:最終的にNOVEL WORK Hongoに決定したのは、オフィスの色味や雰囲気が自社のブランドカラーとマッチしていたことが決め手です。弊社はコンシューマー向けのため、全体的にピンクっぽい暖色系のトーンを好んでいるため、NOVEL WORK Hongoの優しい雰囲気はまさに弊社にとってぴったりでした。
また、社員同士や訪問した人同士がコミュニケーションしやすい十分な広さの環境、具体的には12席ほどを確保できる20坪前後の広さだったことも、選定理由のひとつです。

フレックス制度の働き方と、「遊び心」が反映されたカルチャー醸成にオフィスが貢献
―― 物件の決定から実際の引っ越しまでの期間や準備についてお聞かせください。
髙橋さん:2025年3月に移転しました。『Hive Shibuya』に設置していたPCやモニターを運び出し、増えた座席分のPCなどの備品を購入したくらいで、比較的スムーズに移動できています。必要最小限の移転だったと思います。
インターネット回線については、サンフロンティア不動産さんにご紹介いただいた業者さんにお願いしました。施工にかかった約1ヶ月の間は、モバイルWi-Fiで対応しています。また、清掃についてもサンフロンティアグループのビルメンテナンスサービスをご紹介いただき、週1回の頻度でゴミ回収などの清掃を実施いただいています。契約や打ち合わせもスムーズで、ほぼメールでのやり取りと現地で5分程度の打ち合わせだけで完了しました。
―― NOVEL WORK Hongoに入居しての第一印象はいかがでしたか。
髙橋さん:セットアップオフィスですので、弊社が入居する前からある程度、オフィスの雰囲気は決まっていますが、やはりシェアオフィスとは違って自分たちの世界観をオフィスの空間にも反映させていく過程が楽しいですね。ぬいぐるみやカード、本など自分たちが好きなものを好きな場所に置いて、メンバーや卒業生と撮影したチェキを飾るのも楽しいです。キャラクターのぬいぐるみは社員それぞれを象徴したものを選んでおり、議論が煮詰まった際の雰囲気を和らげたり、コミュニケーションの潤滑油のような役割を果たしたりと、カルチャー醸成に貢献しています。
コンシューマー向けの事業ならではの「ユーザーと共有できる楽しさ」を重視した遊び心ある空間は、自分たちだけのオフィスでなければできなかったことで、弊社が目指す「日常を色づける体験」を形にしたような場所になっていると感じています。
―― オフィスに訪問された方からはどのような反応がありましたか。
髙橋さん:弊社のメンバーは東京大学の学部生や院生が多く、講義後すぐ来られる距離感というのはとても重要です。生活圏内で友人もできやすいですし、フレックス制度の中でふらっと来て、ふらっと帰る働き方が実現しやすいことは、今後の採用活動でも強みになるはずです。実際に、本郷や御茶ノ水などを中心に近隣にはテック系のスタートアップが多く集まっている印象で、少しずつ横のつながりを増やしています。
また弊社に投資いただいているEast Venturesの金子さんに、オフィス移転直後に遊びに来ていただきました。移転にかかったトータルの費用をお伝えしたところ、「いいオフィスを選んだね」と評価していただけています。

「毎日が経営合宿のよう」。積極性と濃度が高まったコミュニケーションが事業を前に進める
―― セットアップオフィスへの移転で、どのような成果が得られましたか。
髙橋さん:オフィス移転のコストを抑え、リソースに限りがあるスタートアップ企業が本当に注力すべき領域に投資できたことが、大きなメリットです。もしオフィスの什器や内装など、すべて自前で揃える形で移転していたとしたら、およそ1.5倍のコストはかかっていたと思います。スタートアップ企業にとって、その差は間違いなく大きいですね。
オフィス移転のきっかけでもあった、出社とリモートのハイブリッドから出社をメインにした働き方へのシフトは無事に成功しています。実際に以前よりも出社率が上がり、対面でのやり取りが増えたことで、気軽な相談がしやすくなりました。さらに、その場でのスピーディな意思決定ができるようになったことは、事業スピードの向上に間違いなく貢献しています。
―― 会社のカルチャーに変化はありましたか。
髙橋さん:大きく変化したと感じます。以前は「こういう提案したいけど、準備が大変だしやめておくか」といったアイデアを出す前にコミュニケーションコストを考慮して諦めてしまう空気がどこかあったのですが、現在ではメンバーから積極的に「これやってみませんか」と声が上がるようになったのです。毎日が経営合宿のような環境で互いの距離が近くなり、社内全体がフラットになってきたなと感じます。常に同じ空間にいて、自然と会話が生まれ、そこから会社としての一体感やスピード感が出てきました。そして今後はよりよいサービス開発にもつながっていくはずと期待しています。
―― その他にオフィス移転による成果があればお聞かせください。
髙橋さん:これまで3分の2ほどだった採用決定率が、今は4分の3くらいまで上がっていると感じています。けっして母数は多くありませんが、確実に採用への好影響はあるはずです。スタートアップはどうしても知名度がなく、怪しげに見えてしまう部分も多々あると思うのですが、実際にこうして整ったオフィスを学生に見てもらえると「ちゃんとした会社なんだな」と信頼してもらえます。
そして経営者として、このオフィスに見合ったグロースをしなければという責任感が湧きました。一国一城の主になった気分ではありますが、それだけにしっかり次のステップを意識しなければと気が引き締まりました。

「日常の中に生きがいを届けるプロダクト」を生み出すため、遊び心あるオフィスを目指して
―― スタートアップ企業にとって、自社でオフィスを持つことにどのようなメリットがあると考えていますか。
髙橋さん:やる気の面で大きなメリットがあります。現在のセットアップオフィスに移転して、オフィスの雰囲気が社員のやる気に与える影響はとても大きいのだと改めて感じました。自分たちが想像する“いい空間”で働くことで、自然と前向きな気持ちになれますし、メンバーもポジティブな状態でいいアイデアを出せるようになります。
個人的には天井の高さもオフィスでは重要だと考えています。物理的に広がりがある空間だと気持ちにも余裕が生まれ、自然とアイデアも出やすくなるのではないでしょうか。
―― 理想のオフィス像と、今後の事業の展望についてお聞かせください。
髙橋さん:事業が成長して次のステップに進んだとしても、遊び心は忘れたくないですね。私たちが目指しているのは「日常の中に生きがいを届けるプロダクト」です。ユーザーの時間と気持ちが少しでも豊かになるようなプロダクトを創っていく場所として、オフィス自体も自分たちも楽しくいられる空間でありたいと考えています。
プロダクトの成長次第ではありますが、「強い人たち」が集まる40名規模の組織が理想です。エンジニアとマーケティングなど、ものをつくる人と届ける人の両輪がしっかりと噛み合った体制をつくっていければと考えており、そのためにも自発的に出社したくなるオフィスを今後も目指していきたいですね。
また、本郷周辺はテック系のスタートアップが多いエリアです。いずれはこのオフィスをふらっと立ち寄ってアイデアを語り合えるような、“サロン”のような場にもできればと考えています。私が主催しなくても自然と誰かが友人を連れてきて、そこから新しい何かが生まれていくような、コミュニティのハブになれたら理想ですね。
―― ありがとうございました。