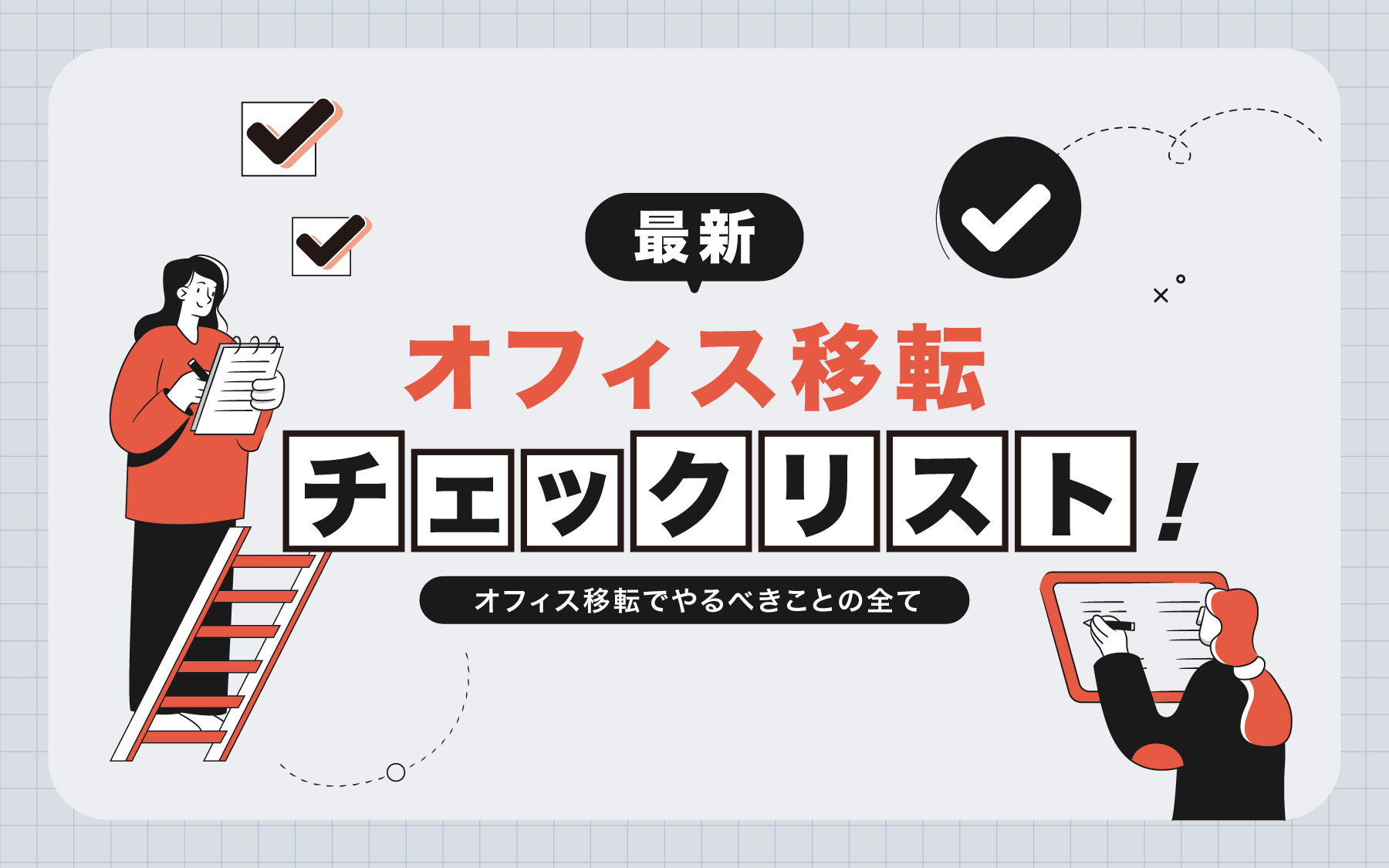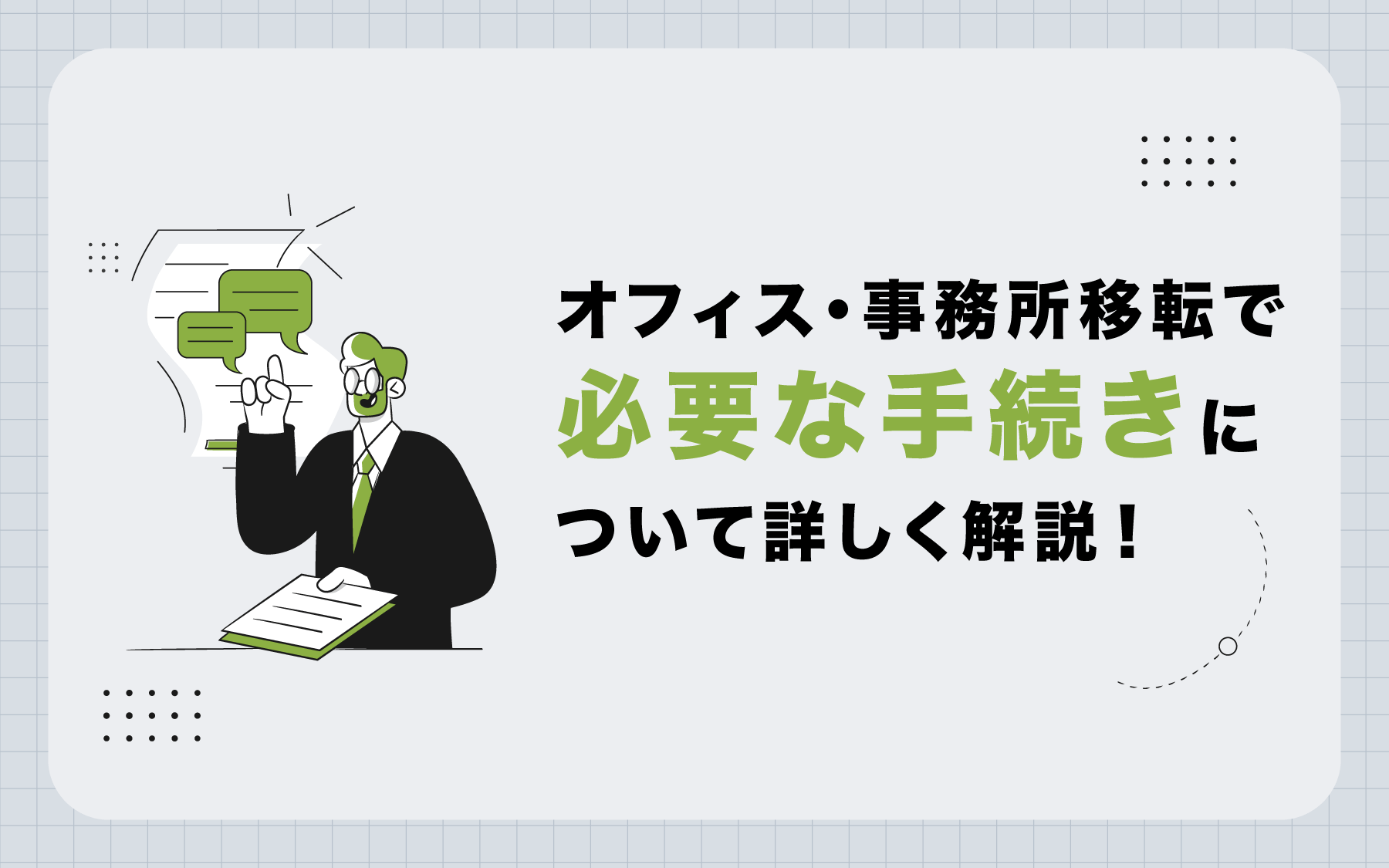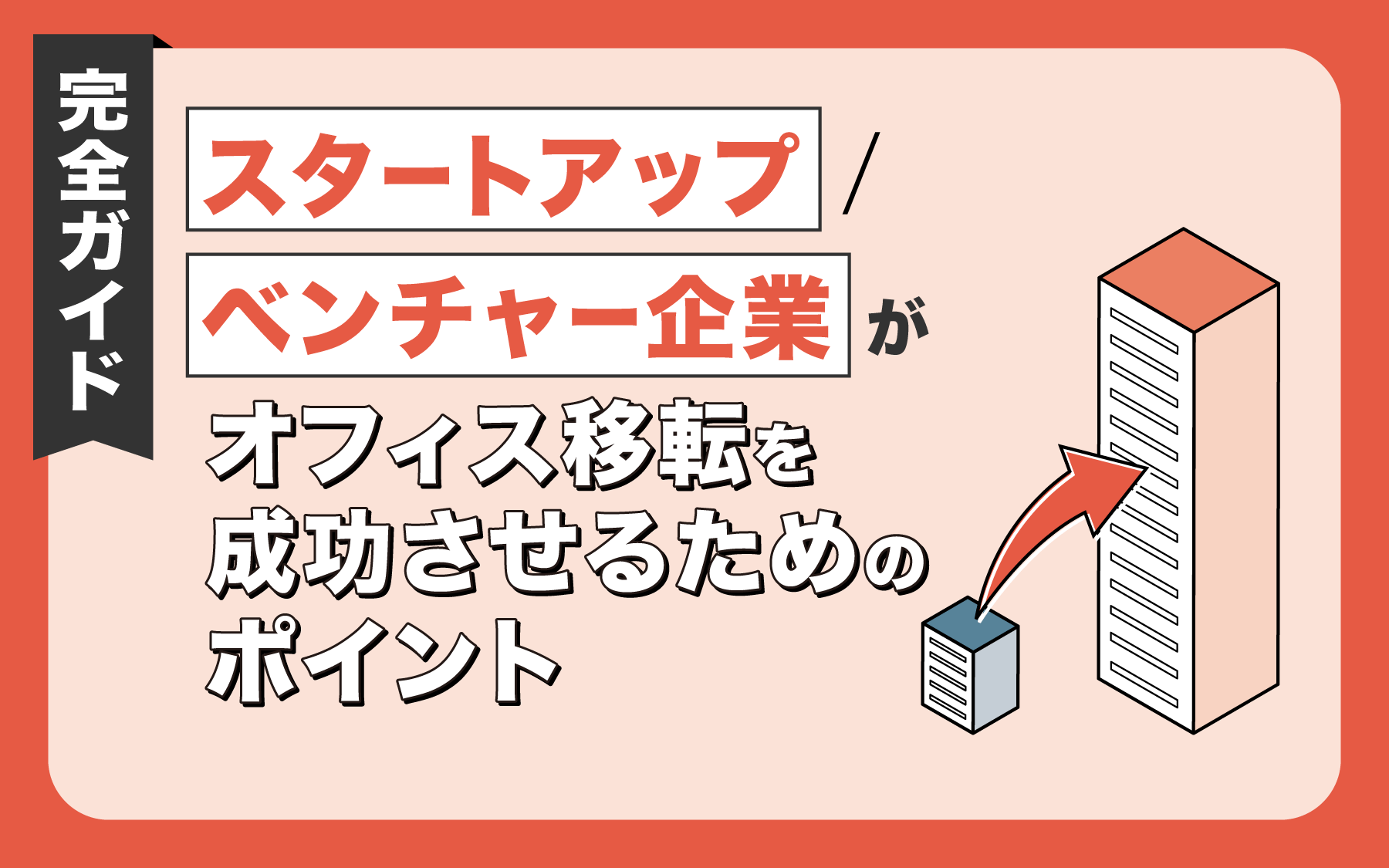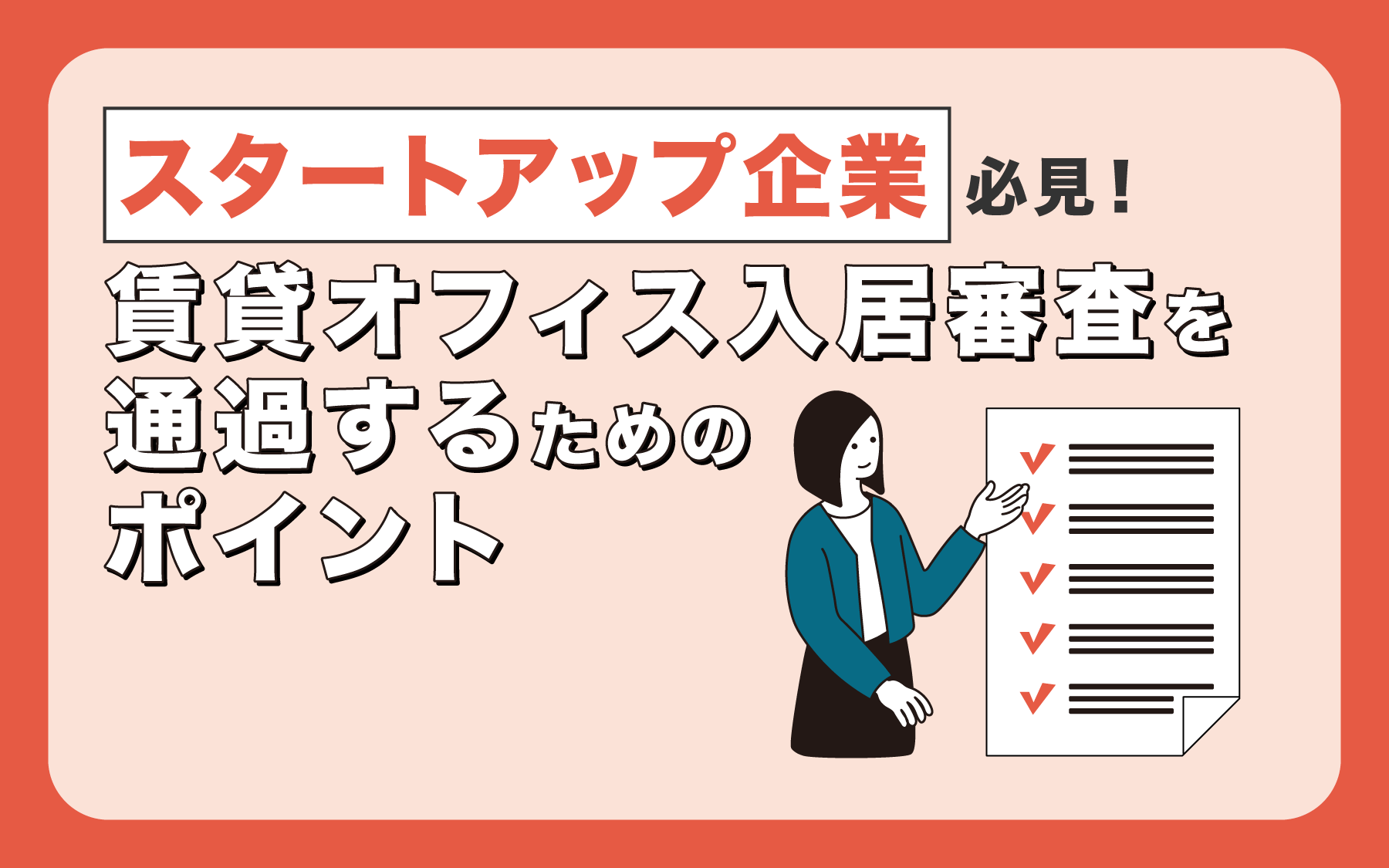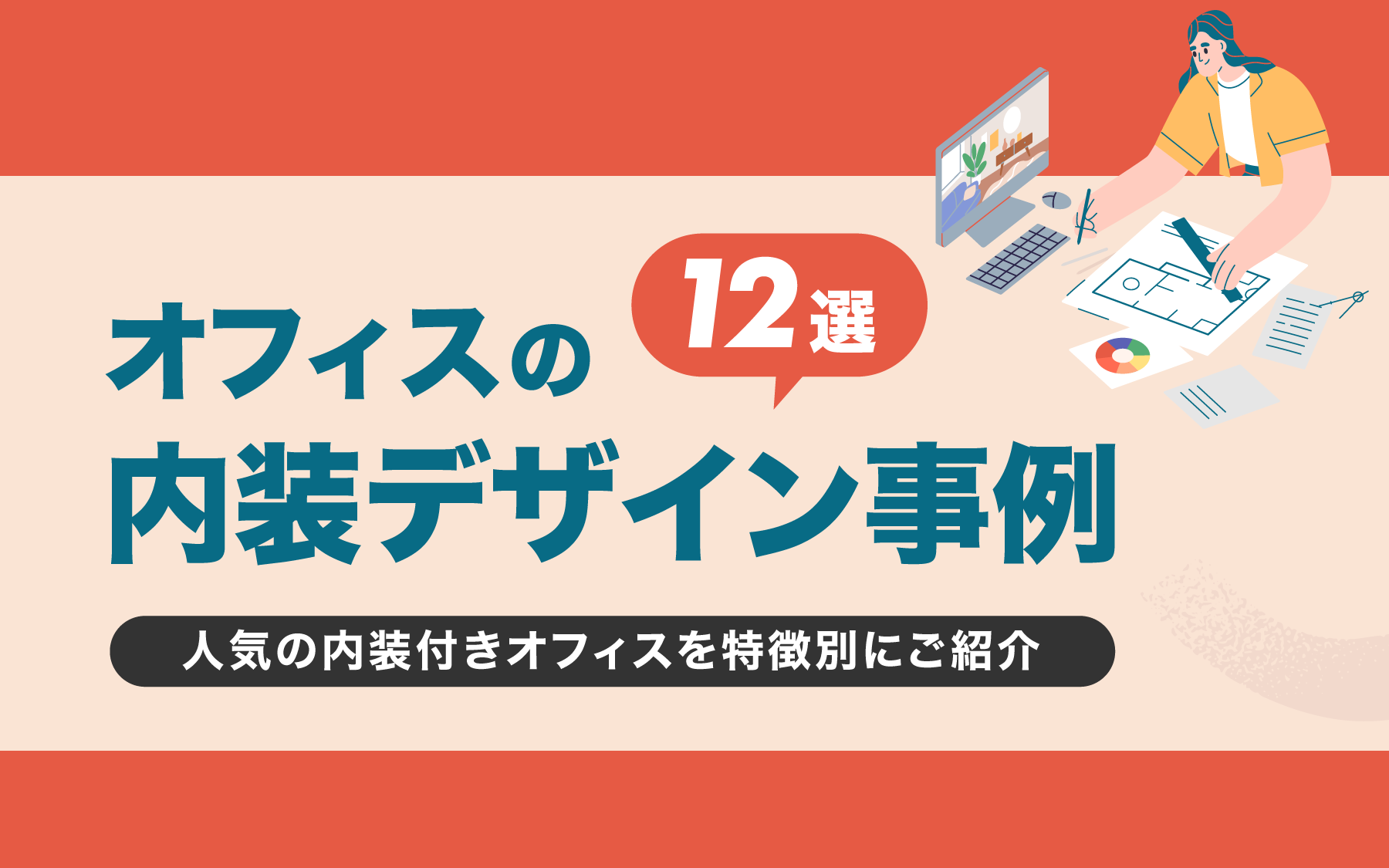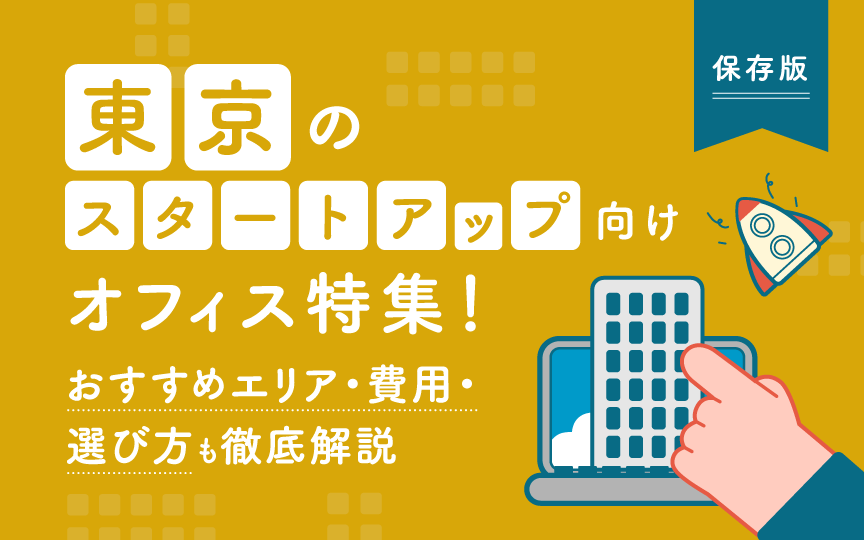法人のオフィス賃貸借契約で「連帯保証人」は必ず必要?保証会社利用との違いも解説
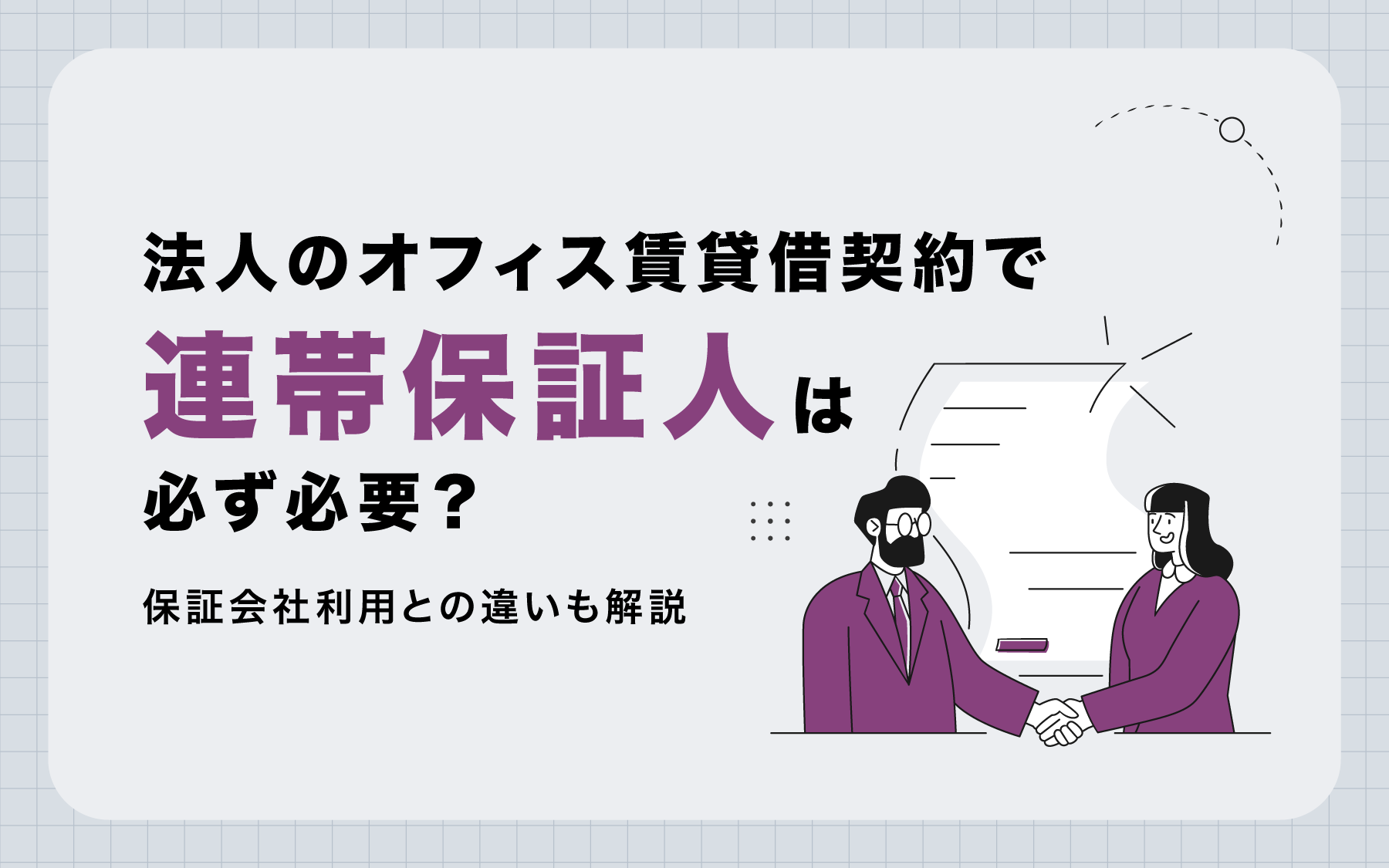
目次
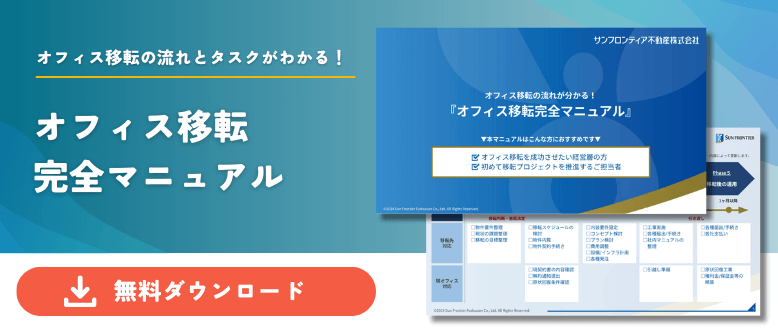
法人がオフィス移転を検討する際、多くの経営者や担当者が直面する問題が「オフィス賃貸借契約の手続き」です。特に、法人契約における「連帯保証人」の扱いについては、誰が連帯保証人となるべきなのか、そもそも連帯保証人は必要なのか、保証会社を利用する選択肢はないのかというように、契約に関する疑問が尽きないでしょう。
本記事では、そんな「オフィス賃貸借契約の手続き」に頭を悩ませる経営者やプロジェクト担当者の方に向けて、法人がオフィスを契約する際の連帯保証人の扱いや、保証会社を利用する場合との違いなどについて、詳しく解説します。
法人契約時の注意点や必要書類についても詳しくまとめていますので、ぜひオフィス移転を進める際の参考にしてください。
目次
法人契約では連帯保証人が必要なケースが多い
まず前提として、法人がオフィスを賃貸借契約する際には、連帯保証人、もしくは家賃保証会社の利用を求められることがほとんどです。法律で定められた義務ではありませんが、貸主(オーナー)が家賃滞納といったリスクを回避するために、契約条件として設定しているのが一般的です。
特に、設立から間もないスタートアップ・ベンチャー企業や、財務状況が安定していない法人の場合、社会的信用力が十分でないと判断され、連帯保証人を求められる傾向が強くなります。貸主からすれば、法人の信用力を補う存在として連帯保証人を立ててもらうことで、安心して物件を貸し出すことができるということです。
連帯保証人は、特に設立から間もないスタートアップ・ベンチャー企業や、財務状況が安定していない法人にとって、円滑な契約締結のために重要な役割を担っていると言えるでしょう。
法人契約の連帯保証人は「代表者」が一般的
法人がオフィスを借りる際の連帯保証人は、その代表者(代表取締役)が担うのが一般的です。よって、多くのケースで「代表者=連帯保証人」という構図になりますが、物件や貸主の方針によってはさらなる保証を求めて、「代表者の親族」など、代表者以外の第三者を連帯保証人として指定するケースもあります。
なお、この「第三者」については、誰でも連帯保証人になれるわけではなく、安定した収入があるか、反社会的勢力と関わりがないかなど、個人の信用力が厳しく審査されます。
家賃保証会社の利用が可能な場合もある
近年、法人のオフィス契約においても「家賃保証会社」の利用は一般化しています。
個人(代表者、あるいは代表以外の第三者)で連帯保証人を立てることが難しい場合でも、家賃保証会社を利用することで法人契約を結べるケースが増えており、むしろ物件によっては、「加入必須」となっているケースも少なくありません。
そもそも「家賃保証会社」とは、万が一借主である法人が家賃を滞納した際に、法人に代わって貸主への支払いを立て替えるサービスを提供する会社です。信用力のアピールが難しい設立5年未満の法人や従業員数が少ない法人にとっては、家賃保証会社の利用が審査を通過するための有効な手段となります。また、代表者やその家族が法人の連帯保証人とならず、個人的なリスクを負うことなく契約できる点も、大きなメリットと言えるでしょう。
ただし、保証会社を利用する際には「保証料」の支払いが必要となることには注意が必要です。費用は物件や保証会社によって異なりますが、契約時に賃料の1ヶ月分、以降は1〜2年毎に更新料が発生するのが一般的です。
出典:家賃債務保証市場に関する調査を実施(2025年) | 矢野経済研究所
連帯保証人と家賃保証会社利用の違い
個人の連帯保証人を立てる場合と、家賃保証会社を利用する場合では、「責任の所在」と「費用」「信用力の補完」「手間・心理的負担」の4つの側面で違いがあります。
| 項目 | 連帯保証人 | 家賃保証会社 |
| 責任の所在 | 法人と同等の重い返済義務を負い、個人の資産で弁済するリスクがある。 | 滞納家賃の支払いを代行するため、リスクを保証会社に移転できる。 |
| 費用 | 不要 | 初回保証料や更新料などの費用が発生する。 |
| 信用力の補完 | 保証人個人の資力や社会的信用に依存する。 | 会社の信用力を補い、審査に通りやすくなる効果が期待できる。 |
| 手間・心理的負担 | 手続きは比較的シンプルだが、「個人として賃料等の債務を背負う」分の心理的負担が大きい。 | 保証会社へ費用を支払うことで、金銭的・事務的な手続きで完結し、心理的負担は少ない。 |
連帯保証人と保証会社どちらも必要となる場合も
通常のオフィス物件の法人契約では、連帯保証人と家賃保証会社いずれか一方で問題ないケースが一般的ですが、物件によっては、連帯保証人と家賃保証会社の両方を求められるケースもあるため注意が必要です。
こういったケースは、主に貸主側が家賃滞納リスクを最大限に回避したいと考え、「代表者個人の保証」と「保証会社による保証」という二重の担保を求める場合に発生します。もし両方を求められた場合、借主である法人は、家賃保証会社との契約手続きおよび保証料の支払いに加えて連帯保証人を用意し、その関連書類を提出しなければなりません。
法人の連帯保証人に関する注意点
法人のオフィス契約で連帯保証人を立てる際には、いくつかの重要な注意点があります。特に2020年4月に施行された「改正民法」は、連帯保証人の責任範囲に大きな影響を与えるため、経営者はその内容を正確に理解しておく必要があります。
出典:民法(債権関係)の改正に関する説明資料(PDF)|法務省民事局
1.民法改正と連帯保証人の極度額
2020年4月1日に施行された「改正民法」により、個人が連帯保証人となる賃貸借契約においては、保証人が負う責任の上限額である「極度額」を契約書に明記することが義務付けられました。
この改正は、個人保証人が無制限の責任を負うことを防ぎ、過度な負担から保護することを目的としており、極度額の金額に法的な上限はありませんが、一般的には賃料の1〜2年分程度で設定されるケースが多いです。
これからオフィス契約を結ぶ際はもちろん、2020年の改正以前から続く契約を更新する際にも、このルールが適用されます。もし、この極度額の定めがない場合、その保証契約自体が無効となってしまうため、契約書に極度額が明記されているか、またその金額が妥当であるかを必ず確認することが、契約上極めて重要です。
連帯保証人が法人の場合の極度額について
ここまで解説した「改正民法」について一つ押さえておきたいのが、「極度額」設定の義務は、あくまで連帯保証人が「個人」である場合に適用されるルールであるという点です。
例えば親会社が子会社の賃貸借契約の連帯保証人になるケースのように、連帯保証人が「法人」である場合には、極度額を設定する必要はありません。
“3 前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。”
出典:「第465条の6【公正証書の作成と保証の効力】」民法 | e-Gov 法令検索
これは、「改正民法」が個人を過度な負担から保護するという趣旨によるものであり、法人間の契約には適用されないためです。したがって、法人が連帯保証人となる場合、契約書に別段の定めがなければ保証の範囲に上限が設定されない点に、十分注意してください。
2.信用調査は個人契約よりも厳格に行われる
法人がオフィスを借りる際の入居審査は、個人の住居契約に比べて、より厳格な信用調査が行われるのが一般的です。これは、法人のオフィス契約が個人の住居契約よりもはるかに大きな金額の契約となることから、貸主が法人の安定性や支払い能力を慎重に見極める必要があるためです。
審査では、会社の登記簿謄本や決算書といった書類の提出が求められます。実績の少ないスタートアップ企業の場合は、事業計画書の提出を求められ、将来性や収益見込みが重要な判断材料となることもあります。
さらに、調査の対象は法人だけにとどまりません。会社の信用力を補うものとして、代表者や連帯保証人個人の信用情報も合わせて確認されることが多くあります。スムーズに審査を通過するためには、必要書類を事前にしっかりと準備し、自社の支払い能力を明確に示せるようにしておくことが重要です。
3.支払いが滞った場合は信用情報への影響がある
万が一、オフィスの家賃支払いが滞ってしまった場合、その影響は契約者である法人だけでなく、保証の主体である連帯保証人にも及びます。
個人が連帯保証人となっている場合、滞納が即座に信用情報機関へ登録されるわけではありませんが、連帯保証人は借主本人と同等の支払い義務を負っています。そのため、貸主が裁判所に訴えを起こし支払いを命じる判決が出た場合など、法的な手続きに発展した際には、その事実が連帯保証人個人の信用力に大きな悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。
契約者自身にとっても連帯保証人にとっても、家賃の滞納は将来の資金調達や新たな契約に支障をきたす重大な問題です。支払い計画には細心の注意を払うようにしてください。
4.代表者を退いても、連帯保証人の地位は残る
最後に、経営者が注意すべきこととして、会社の代表者を退任しても連帯保証人としての契約上の地位は自動的には消滅しない、という点があります。これは、連帯保証契約があくまで貸主と保証人個人との間で結ばれるものであり、会社での役職とは切り離して考えられることが理由です。
したがって、後任の代表者に事業を引き継いだとしても、特に手続きをしなければ、元代表者は退任後もその会社の家賃債務を保証し続けることになります。これは、自身が関与しない会社の経営リスクを永続的に背負うことを意味し、非常に危険な状態です。
このリスクを回避するために、代表者の交代時に貸主の承諾を得た上で、連帯保証人を新代表者へと切り替える手続きが不可欠です。実務上、貸主も会社と無関係になった人が保証人であり続けることを望まないため、適切な後任を立てることで交代が認められるケースがほとんどです。退任時には、必ず保証人契約の変更手続きを行うようにしてください。
オフィスの法人契約で必要な書類
オフィスの賃貸借契約を進めるにあたり、法人契約では特有の書類が複数必要となります。手続きをスムーズに進めるためにも、申込時と契約時、それぞれの段階でどのような書類が求められるのかを事前に把握しておくことが大切です。
法人のオフィス申込時に必要な書類
まず、入居審査を受けるための「申込時」には、主に法人の信用力や事業実態を証明するための書類を提出します。一般的に必要となるのは、以下の書類です。
■法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
法人の正式名称、所在地、代表者名などが記載された公的な証明書です。法務局で取得でき、通常は発行から3ヶ月以内のものが求められます。
■会社概要の分かる資料
事業内容や設立年、従業員数といった会社のプロフィールがわかる資料です。会社のウェブサイトやパンフレットのコピーでも構いません。設立間もない法人の場合は、今後の事業計画書を求められることもあります。
■決算書
法人の財務状況を示すための重要な書類です。一般的には、直近3期分の提出を求められます。設立1期未満の法人や、決算期から半年以上が経過している場合には、月次の試算表など、足元の業績がわかる書類の提出が必要となるケースもあります。
■代表者の身分証明書
契約の主体となる法人の代表権を持つ人物であることを確認するため、代表者の運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーを提出します。
連帯保証人が必要な場合の追加書類
賃貸借契約の条件に連帯保証人が含まれる場合は、先に挙げた法人の書類に加えて、連帯保証人個人の信用力を証明するための書類が別途必要になります。
主には保証能力を確認する目的で、源泉徴収票や課税証明書といった収入を証明する書類の提出を求められるのが一般的です。これらの書類は申込時までに用意する必要がありますが、連帯保証人を立てることが決まった段階で早めに準備を依頼しておくと、その後の手続きが滞りなく進みます。
法人のオフィス契約時に必要な書類
入居審査を無事に通過すると、最終的な契約締結のステップに進みます。この段階では、申込時に提出した書類の原本や公的書類の提出が求められます。
法人として必要になるのは、発行から3ヶ月以内の「法人登記簿謄本」と「法人印鑑登録証明書」の原本です。契約書には法人の実印で捺印するのが一般的であるため、その印影が正式なものであることを証明するために印鑑登録証明書が不可欠となります。
連帯保証人を立てている場合は、連帯保証人個人の「住民票」と「印鑑登録証明書」の原本も同時に提出します。契約当日には、法人の代表者が契約書に署名と実印の捺印を、連帯保証人が連署と実印の捺印を行います。書類に不備があったり必要な印鑑を忘れたりすると契約が締結できないため、不動産会社からの案内に従って、事前に漏れなく準備しておきましょう。
保証会社を利用する場合の追加手続き
法人が連帯保証人を立てずに家賃保証会社を利用する場合、契約時には法人と貸主との賃貸借契約に加え、法人と保証会社との間での手続きが別途必要になります。
具体的には、まず保証会社が指定する「保証委託契約書」に署名・捺印をします。これは、法人が保証会社に家賃債務の保証を正式に委託するための契約です。
次に、契約金の一部として「初回保証委託料」を支払います。この保証料は、敷金や仲介手数料など他の初期費用と一括で請求されるのが一般的です。この保証委託契約の締結と保証料の支払いが完了して初めて保証の効力が発生し、正式に賃貸借契約が成立します。
法人のオフィス契約をご検討中の場合は、ご相談ください
今回の記事では、法人がオフィスを契約する際の「連帯保証人」の必要性や、「家賃保証会社」を利用する場合との違い、民法改正に伴う注意点、さらにはオフィスの賃貸借契約にあたって必要な各種書類等について解説しました。
連帯保証人・家賃保証会社のどちらを選択するかは、法人の状況や貸主の条件によって異なり、手続きが複雑に感じることもあります。特に、設立間もないスタートアップ・ベンチャー企業にとって、信用力の証明や煩雑な書類準備は大きな負担となり得るでしょう。
もし、オフィス移転の進め方や先々の契約手続きにご不安やお困りごとがございましたら、ぜひ一度オフィス不動産のプロであるサンフロンティア不動産にご相談ください。豊富な経験と実績で積み上げた知見をもって、貴社のオフィス移転を強力にバックアップいたします。
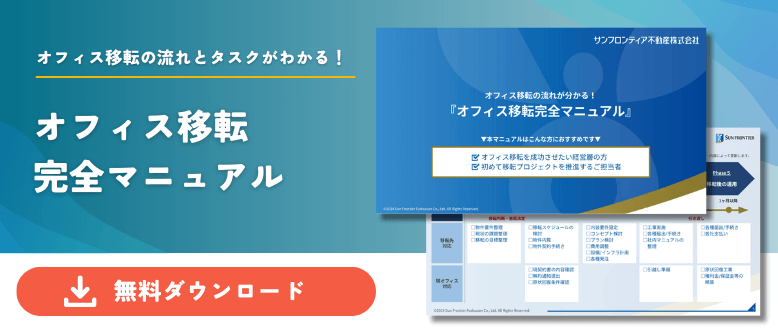

記事監修者
菅野 勇人
宅地建物取引士
セットアップオフィスから一般的なオフィスまで、多種多様なオフィスビルの魅力や特徴を熟知したオフィス物件マニア。
スタートアップ企業の移転支援経験が多く、そこで得た知見を活かし、お客様の理想のオフィス探しを全力でサポートいたします。